「上からの圧力がヤバくて、毎日ストレスが半端じゃない」
「何が楽しくて自分を追い込んでいるのか分からなくなってきた」
このようにインセンティブの仕事独特の悩みに直面してメンタルが落ち込んでいる方は多いです。
ノルマや成果によって評価や生活も変わるので、モチベーションの上がり下がりが激しくストレスを抱えやすい職種とも言えますよね。
そこで当記事ではインセンティブをモチベーションにすると危険な心理学と3つの解決策について徹底解説していきます。
さらにインセンティブをモチベーションにした失敗例も紹介しているので、今の自分自身と取らし合わせてみてみることをおすすめします。
インセンティブをモチベーションにすると危険な3つの心理学

結論から言うと、インセンティブをモチベーションにすることが長期的に見るとデメリットしかありません。
短期的には「稼ぎたい」気持ちがモチベーションになるかもしれませんが、長い目で見ると得られるものが少ないことは明らかです。
本章ではインセンティブをモチベーションにすると危険な3つの心理学について下記を中心に解説していきます。
- メンタルが安定しない
- 仕事に対する満足度が一定以上は上がらない
- 自分の時間を見失う
メンタルが安定しない
インセンティブが高い新しい仕事を始める際に最初から上手くいくことは困難でしょう。
なぜなら会社に入っても技術やスキルがいまいち共有されずに自分で体当たりしなければならないからです。
例えば営業成績1位の方が他の人にそのメソッドを教えるメリットはありません。
なぜならうまくいく方法を伝えると自分の利益が少なくなる可能性が上がるからです。
仕事に対する満足度が一定以上は上がらない
インセンティブで給料が上がっていっても仕事に対する満足度は一定以上は上がりません。
それよりも私たちのモチベーションや満足度を上げてくれるものは「人間関係」です。
なぜかというと良い人間関係が築けていると自分の居場所が認識でき、自分自身を認めてくれる人が周りにいるだけで自己肯定感が上がります。
インセンティブで良い暮らしができたとしても美味しいご飯を食べ続けられないように、数日でその生活には慣れてしまいます。
さらにインセンティブだけを仕事のモチベーションにすると、会社自体が稼げなくなると今までやってきたことの自分の行動や価値さえ疑い始めます。
一生安泰な会社なんてありませんからね。
自分の時間を見失う
毎月成果を上げなければインセンティブによる報酬を確保できじ生活が危ぶまれます。
見込み客や契約間際など成果になりそうなことが目の前にあれば休日も関係ありません。
友人、恋人、家族などプライベートな時間であっても、仕事の良い話があれば天秤がお金になります。
インセンティブのために色々なことを犠牲にして手元に残ったお金も使えばなくなります。
ですが、大事な人たちと共有する時間はその瞬間でしか生まれません。
インセンティブをモチベーションにすることで、周りと向き合うことを忘れてしまうのです。
インセンティブをモチベーションにするメリット・デメリットの違いとは

インセンティブをモチベーションにするとどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
本章ではインセンティブをモチベーションにするメリット・デメリットの違いについて下記を徹底解説していきます。
- 2つのメリット
- 2つのデメリット
2つのメリット
まずはメリットから解説していきます。
解説する内容は下記の通りです。
頑張った分だけ実績や成果が還元される
インセンティブのない会社ではどれだけ頑張った人でも頑張らなかった人でも毎月同じ給料が固定されています。
そのため「頑張っても頑張らなくても一緒でしょ」という社員も生まれやすくなるのです。
さらに仕事ができる、できないに関わらず上司や経営陣に好かれているかで中小企業などは賞与も変わっていくもの。
ですが、インセンティブ制度があれば頑張った人にはきちんと成果が対価や報酬として還元されます。
このように社員の意欲に対して線引きがされるため、頑張り損にならず報われる感覚を味わえるでしょう。
立場や経験関係なく評価される
企業に入社すると社歴や経験から出世までに時間もかかります。
数年、成果が出せていない社員よりも給料が低いなんてこともざらです。
徐々に階段を登らせる体制とは反対にインセンティブ制度では目に見える実績が第一と言えます。
3年目の社員よりも入社して数か月の社員の方が収入が多いなんてことも珍しくありません。
実力で評価されたい方にとってはメリットと言えるでしょう。
3つのデメリット
メリットがあるということはデメリットもあります。
続いて下記のインセンティブをモチベーションにする3つのデメリットについてです。
次節より詳しく解説していきます。
収入の不安定さ
インセンティブでは毎月の収入が安定せずメンタルも不安定になりがち。
10万の月もあれば30万の月もあるなど、ばらつきが激しければ余計に生活の不安がつきまといます。
そして不安を抱えたまま仕事をしてしまうと本来のパフォーマンスが発揮できずに、自分自身を「出来ない人」と自己否定してしまう可能性も。
大きなプレッシャーによる精神的負担
インセンティブに重きを置いている会社は成果を出せない人間を詰めます。

なぜ契約が取れないんだ、ちゃんと仕事してるのか。

やる気あるの?契約取れてないの君だけだよ。
このように数字が正義のため「なぜできないのか」を問い詰めてくるでしょう。
目上の方に圧迫されてプレッシャーに感じない人はいませんし、自責の念にかられますよね。
そのプレッシャーが精神的な負担になり、次第に会社に行くことすら恐さを感じ始めます。
休日も稼働しなければならない
稼働する時間が増えれば増えるほど成果報酬を高める可能性が上がります。
そのためインセンティブを得るために休日を犠牲にしている人も少なくありません。
担当エリアがバッティングしてしまうと、立場が上の人が奪う可能性も上がります。
しかし先に見込み客として自身の名前を売って置ければ手を付けられずに済むでしょう。
土日であっても、就業後であっても電話やメールは惜しまないため自分の時間を失ってしまい「仕事だけ」の人生になってしまいます。
インセンティブをモチベーションにした4つの失敗例を紹介

インセンティブのように成果報酬で社員を縛るのは経営者からすれば非常に簡単で分かりやすいマネジメントと言えます。
その反面、成果に重きを置いている分、社員の不満も溜まるもの。
続いてインセンティブをモチベーションにした4つの失敗例について下記を中心に解説していきます。
一部の人間が多くのインセンティブを獲得する
1つ目の失敗例は「インセンティブは一部の人間が多くのインセンティブを獲得する」ことです。
優秀な一部の社員は継続的に固定給+多くのインセンティブを獲得できますが、その他の多くの社員は少ないインセンティブしかもらえません。
優秀な一部の社員以外の大多数のモチベーションが低いと職場全体の空気も悪くなります。
評価されるのはいつも決まった人で、他の人が評価されることもなければ心が折れる人も出てくるでしょう。
離職率が高くなる
2つ目の失敗例は「離職率が高くなる」ことです。
インセンティブをモチベーションにしている成果を出せる優秀な社員は会社に残り続けるでしょう。
ですが、成果を出せない社員は給料も上がらず、充実感も得られず、「自分には向いていない」と会社から離れていきます。
成果に繋がらない仕事がどうでもよくなる
3つ目の失敗例は「成果に繋がらない仕事がどうでもよくなる」ことです。
なぜなら自分の仕事が直接、収入に直結するため成果に繋がらない仕事に時間を割くことはしたがりません。

この業務やったところで、給料増えないでしょ。
このように社員の意欲が低下していき、それは全体への悪影響にも繋がります。
仲間意識が薄れて助け合いが無くなる
4つ目の失敗例は「仲間意識が薄れて助け合いが無くなる」ことです。
基本的に自分のインセンティブを獲得することが最大のミッションですから、他人にかまっている暇はありません。
市場も先に手を出したもの勝ちなところがあるので、社内での競争意識も高いです。
自分が成功したノウハウを他人と共有することを拒みますし、第一優先の全ては「自分」になります。
インセンティブをモチベーションにするのが向いている人と向いていない人の違いはコレ!

インセンティブは性格的に合う人にとっては報酬が良いモチベーションになることは言うまでもありません。
フルコミッションできる性格でリスクに不安を感じず前に進める方が向いているでしょう。
また同じ業界で働いていて、今までのやり方を活かせる方も向いています。
ですが、「上手くいくか心配「成果が出せなかったらどうしよう」と不安に感じる人の方が多いです。
安心しながら安定的に仕事をしたいのであればインセンティブをモチベーションにする仕事は向いていないと言えます。
言い換えれば毎月決まった給料が貰える安定性の中で、違うことに余裕を持ってチャレンジできる方がリスクが少ないと言えます。
またインセンティブを発生させるには仕事のノウハウから勝ちパターンを見つけるまでに時間もかかるため、成果が出る前にメンタルがやられてしまう人が大半です。
安定した会社であれば人材を育てることに力を注いでくれるため、実績が出せなかったとしても何年にもわたって技術・やり方を学びながら給料をもらうことができます。
インセンティブ以外でモチベーションを上げる3つの解決策を徹底解説!

ではインセンティブという報酬に頼らずにモチベーションを上げるためにはどのような方法があるのかについて徹底解説していきます。
インセンティブ以外でモチベーションを上げる3つの解決策は下記の通りです。
次節より一つずつ詳しい詳細を解説していきます。
技術やスキルを身につける
会社や組織に所属する一番のメリットは毎月給料を貰いながら技術やスキルを身につけられることです。
仮に会社が経営困難になったとしても個人の能力があればいくらでも働き口は確保できます。
人はいくらでも補充できますが、能力は替えがきかないポートフォリオになるのです。
仕事で失敗しないロードマップの書き方については以下で解説しているので、参考にしてみてくださいね。
友人関係に近い人間関係を作る
仕事内容がどんなにやりたいことであったとしても、人間関係がよくないとメンタルが持ちません。
反対にあまりやりたくない仕事でも、社内に友人に近い人間関係が築けていれば満足度は上がるもの。
自分に合う良い会社の選び方については以下でまとめているので参考にしてみてくださいね。
自分の時間を大事にする
家から会社へ、会社で仕事をして家に帰ってをするとだいたい1日10時間は仕事に時間を使っています。
そこから睡眠してと考えると自由に使える時間ってかなり限られてますよね。
家と会社の往復を繰り返してばかりいる人生に嫌気がさしている人も多いのではないでしょうか。
家族や恋人、趣味や副業など、どんなことでもいいので自分が大事にしているものに費やせる時間を増やしてください。
モチベーションを下げないために有効な手段は狭い世界で苦しまないことです。
そして楽しみを増やせると仕事の活力としてモチベーションに働きかけてくれます。
仕事ばかりの人生で年を重ねてから「あの時こうしておけば」と後悔の念にかられる前に、生き方と向き合ってみることをおすすめします。
まとめ ~最初からインセンティブの仕事はリスクが高い~

以上、モチベーションをインセンティブで保つと危険な心理学について様々な情報を解説してきました。
まとめとして、最初から新しい業界のインセンティブの仕事をするのはリスクが高いと言えます。
生活費や失敗といった意味合いだけでなく、メンタルの問題が関わってきます。
知識が乏しい業界に入っても最初からインセンティブを獲得できる人は本当に稀です。
大多数の人がインセンティブを獲得できずに自己否定を始めてしまい、メンタルが落ち込んでしまいがち。
やったことがないのであれば、安定を取りながらインセンティブに切り替えていく方がメンタルの上がり下がりが少なく健全に仕事に取り組めますよ。
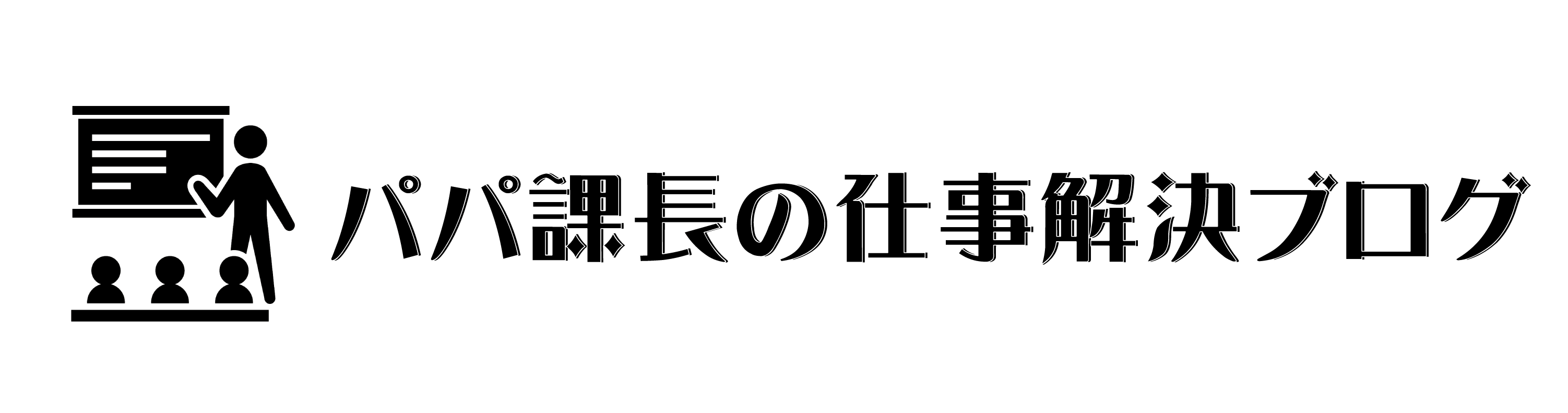
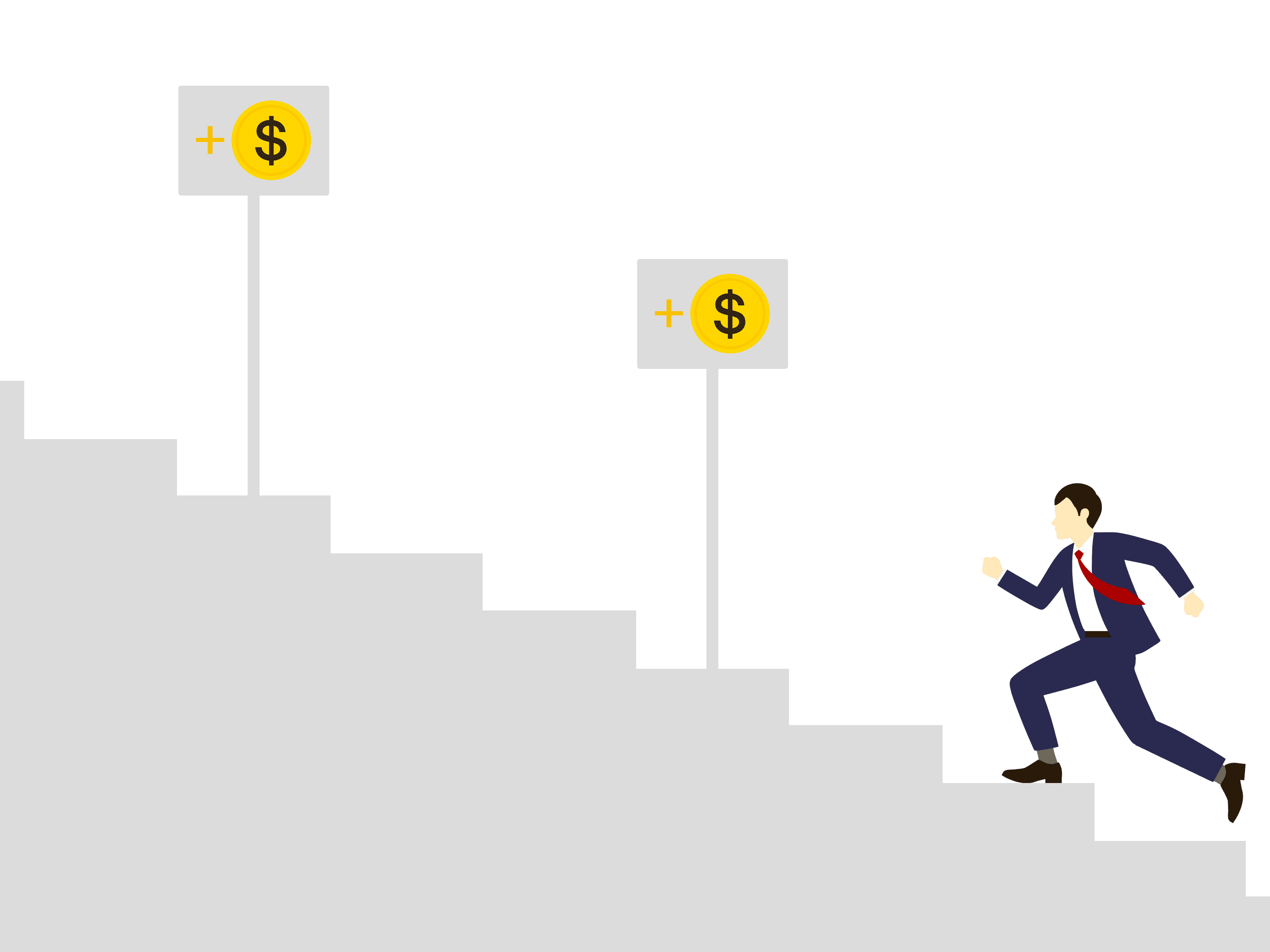




コメント